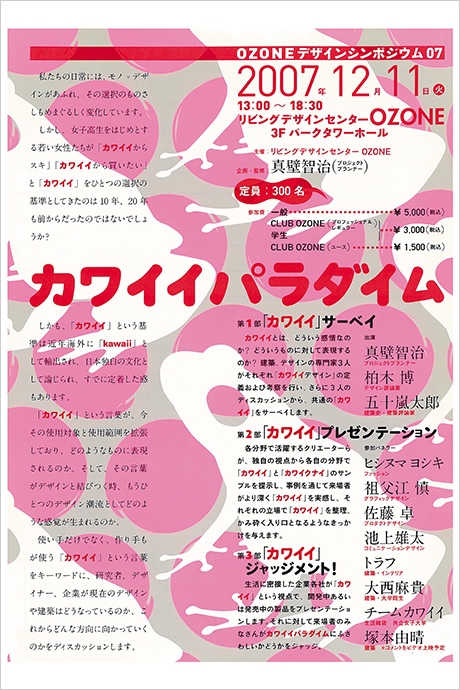東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻修了。M・T・VISION主宰。「建てない建築家。を標榜し、都市、建築、住宅分野のプロジェクトプランニングに取り組む。著書に『カワイイパラダイムデザイン研究』(平凡社)など。2021年日本建築学会文化賞受賞。
コンセプト委員とは、OZONEのコンセプトを考え、総合ショールームに出店するテナントを選ぶ存在。私以外のメンバーはインテリアやプロダクトデザイン関連の方がほとんどでした。そこで、住宅設備や建材メーカーとつき合いがあり、各社の戦略や、これからの住空間に何が必要とされているかをいささか知っている私に声がかかったのだと思います。
OZONEの構想の枠組みにあったのは、住文化の発信拠点と複合ショールーム、さらに人の交流です。この3つの機能を備える施設ならば、手伝うに値するプロジェクトだと思いました。
70年代の住設メーカーは、エンドユーザーに直接会うことはほとんどありませんでした。基本はルートセールス。建材やパーツがタイル店や水道工事業者を通じて販売されていた時代、各社のショールームは銀座にあり、「ここが銀座ですよ」と声をかけながら工務店がお客様を連れて行っていました。
80年代に入り、インテリアや家づくりの雑誌がポピュラーになったことで、一般の人も興味を持つようになりました。エンドユーザーがアクセスしやすいターミナル駅にもショールームが登場。新宿にも、すでに住設や建材のショールームが点在していました。
90年代に入ってOZONEがオープンしたあとは、エンドユーザーを連れた建築家や工務店が複合ショールームとしてのOZONEを訪れ、その後新宿にあるINAX(現LIXIL)やTOTOのショールームにさらに足を運びました。そこに新しい循環が生まれました。
企画会議も大変でしたが、ビルの建築設計を行った丹下健三氏サイドを相手に、空間デザインを担当した田中俊行氏が喧々諤々とプランニングを行っていたのが印象的でした。建築家とインテリアデザイナーでは言語も規範も違うから、お互いの主旨を私が翻訳しなければいけない。大変でしたね。
OZONEは、総合性・中立性・信頼性を備えたプロジェクト。この3つの要素は非常に意味があります。個々のショールームを訪れても、そこで得た情報が信頼性に足るものなのか不明な状態では、ユーザーに不満が残ったままになります。信頼できる中立な相手に相談できる場は非常に重要でした。
30年前の家づくりでは、まず家を建て、その家に合わせて暮らしていました。でもコロナ以降はこれが逆転。まず暮らしがあり、そのなかでどんな家がいいのかを考えるので、標準的な家にこだわりがなく、リノベーションもあればあえて平屋の家に住む人もいます。
住宅業界も大きく変わり、オープン当初は言葉自体がなかったリノベーションが増えました。例えば、ある企業はリフォームに特化したショールームを都心部に作り、都市郊外には新築関係のショールームを展開するなど戦略的に動いていました。
今はソーシャルメディアで多様な情報に触れられる時代。OZONEには、情報を再構築したり、実物を検証したりできる場としての意味が強く求められていると思います。さらに、中古住宅のストックをどのように活用するのか、傷んだ建物をどう補修するのか、行政からの要求にどうやって対応するのかといった家づくりの悩みや障害に対し、解決法を提示できる場であってほしいですね。
コロナ禍によって生活も大きく変化した現在こそ、新しい解釈が求められているのは間違いありません。